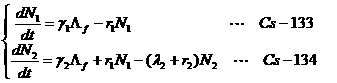問い合わせ先:mahlergstav@gmail.com
CS-134とCs-137の放射能比:(Cs-133) Cs-134が核分裂で生成する項を追加した式を紹介した。
1秒当たりの核分裂数が
となる。 結論を言うと、福島第一原発のような軽水炉では、Cs-134の(n,γ)反応率 反応率を求めるには、ある程度原子炉の知識が必要で、手続きも複雑になる。粗い見積もりであれば、複雑なコンピュータプログラムを組まなくても、辛抱強い人であれば付いていけないほどのものでもない。 理解できるできないに関わらず、どんなものか知らないと気がすまない方、こんなこと少し考えればわかると思う人は、結構な分量になるが、ここを見てほしい。見れば気がすむし、少しぐらい考えてもわからないことを認識できるだろう。これは、壊変モデルに関わるもので、燃焼モデルに比べると、遥かに易しい。これがチンプンカンプンなら、無理して見る必要もなく、読み飛ばしても構わない。 Cs-133が(n,γ)反応を起すと、Cs-134になる。Cs-133は安定同位体のである。β崩壊の確率は0であるから、(n,γ)反応を無視することはできない。Cs-133の(n,γ)反応率も半減期に換算すると、10年ほどになる。これは代表的なβ崩壊の半減期、例えばCs-137の半減期30年よりも短いので、原子炉ではβ崩壊と同等に扱うべきである。そうすると、Cs-134はCs-133の娘核として扱う必要がある。
となる。ここでは、1番目がCs-133で2番目がCs-134となる。 Cs-133は天然に存在するから原子炉中に最初からCs-133が入っていることも考えられないこともないが、セシウムを入れることで大きなメリットも考えられないし、原子炉の燃料や構造材は厳しい品質管理をするので、誤って大量のセシウムを混入してしまうことも考えにくい。もともとセシウムは希少であるから、混入させたくてもできないだろう。 核分裂で直接生じた核分裂片にはCs-133もあるだろう。しかし、Cs-134のように直接生成される確率はCs-134と同等の10の-8乗程度であろうから、このままでは (n,γ)反応によるCs-134を含めても、東電発表のペタベクレルには届きそうもない。Cs-133を生成する他のプロセスがあると考えられる。 壊変モデル へ |